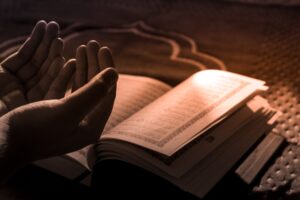対話型生成AIとプラグマティズム
私は対話型生成AIはAnthropic社のClaudeをメインで活用しています。
一般的にはChatGPTのほうが知名度がありますが、文章の読みやすさや、納得感(正しいかどうかは別として)というところでClaudeの方が自分に合っているなと感じました。
私はかつて休日になるとひたすら自己問答を繰り返しながら一人旅をしてきたような人間なので、AIを壁打ちのように使うことはその延長にある行為だなと思いました。
Claudeと哲学的な対話を進めていくと「プラグマティズム(実用主義)」という概念を教えてもらいました。
この19世紀後半にアメリカで生まれた思想は、「真理や価値は実際の経験と実用性によって判断されるべき」という考え方だとされています。
この概念を知った瞬間、長年にわたって漠然と実践してきた自分の思考パターンや行動原理に、明確な哲学的基盤があることを発見し、深い納得を覚えました。
就職氷河期世代の哲学
私は就職氷河期世代のど真ん中の人間なので、「努力すれば報われる」「正しいことをしていれば認められる」といった理想主義的な価値観がもはや崩壊しているという現実を知り、もがきながらなんとか生きてきました。
子供の頃から天邪鬼な性格ではあったものの、このことによって人間や世の中のルールというのは適度に疑っていかなければならないと思うようになりました。
「信念や理想だけでは食っていくことはできない」という認識は、まさにプラグマティズムの考え方と合致しているのです。
だからと言って反社会的な思想に染まるのではなく、自分が生き残っていくにはどうすればいいのか、ということに真剣に向き合った時代でした。
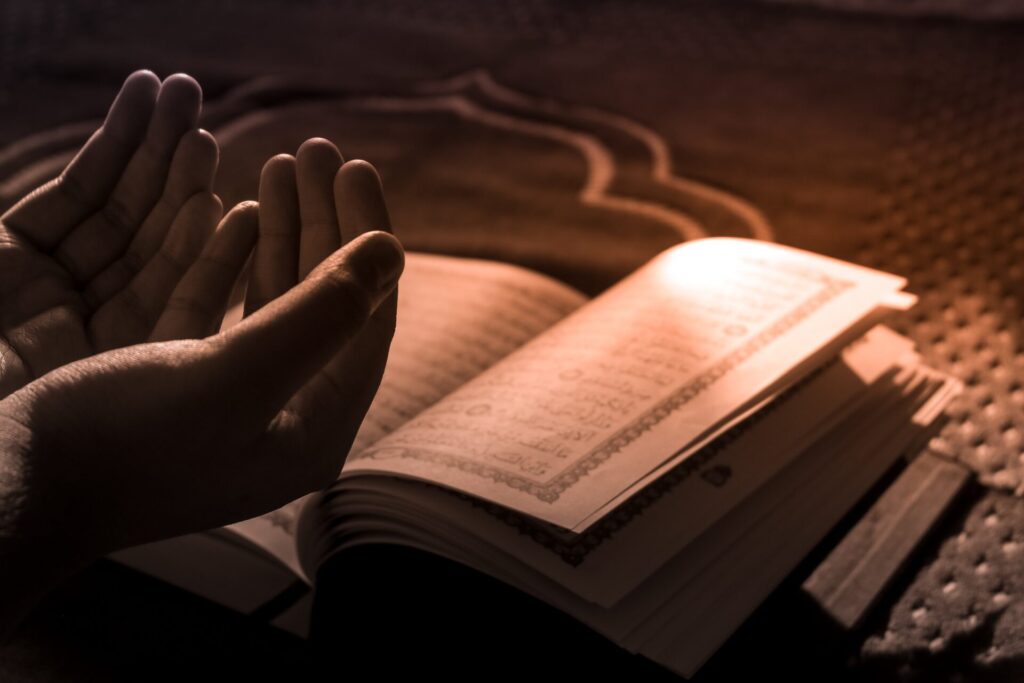
長浜での地域密着戦略
私が長浜市で地元密着主義とする戦略を立てたのも、結果的にはそれが自分が生き残る可能性が一番高いと考えたからです。
私が色々なところで旅をして、長浜市に移住しようと思ったのは純粋に長浜市が気に入ったからというのも事実であり、同時にこの町の規模間や風土などが自分に合っていると考えたからです。
長浜に移住してから、まずはとにかく町内会や地元のイベントに出来るだけ顔を出しました。
何の縁もゆかりもない外から来た自分がここで事業を発展させるためには、まずは近所の方に顔を覚えてもらわなければ始まらないと思いました。
つまり、100%の善意でもなければ自己犠牲でもない。
しかしそうした活動が結果的に地元の方に感謝され、それが仕事に繋がるかもしれない。
欲を出し過ぎてはいけないが、まったくの無償奉仕でもない。
これらは「都合の良い考え方」かもしれません。
しかし、プラグマティズムの視点から見れば、これは理想と現実を統合した健全で持続可能な社会参加の形であることが明確になりました。

投資における実利主義
私は2018年頃から個人的に投資を始めてきました。
コロナショックを乗り越え、2~3年もするとそれなりの結果を出すことができました。
最初は日本企業の株を個別的にいくつか買うところからスタートしたのですが、今は専らS&P500のインデックスファンドに投資しています。
「日本国内に投資せず、海外に資金を流出させているのでは国に貢献しているとは言えない」という人もいますが、
投資というのは慈善事業ではなく結果にコミットしなければいけないので、赤字を出しては意味がありません。
私はS&P500への投資に切り替え、そのリターンがあったからこそ、その資金を行政書士の開業のために使い、長浜で活動するための基盤とすることができました。
これもまた理想を主張するだけではなく、実利を伴ってこそ持続活動性があるというプラグマティズムの考え方に合致するものだと納得することができたのです。

音楽活動での実利と理想
長浜市における音楽活動も、子どもたちに音楽を教えたりする機会を作ってもらうことで、その文化の発展に貢献したいという想いがあります。
しかし完全に無償奉仕で終わるだけではなく、それがもしビジネスに繋がるのなら積極的に掴みにいきたい。
これは個人事業主ならではの自由度も相まって、理想と実利の両方から考えた行動ができるのだろうと思います。
プラグマティズムという理論的枠組みを得たことで、理想論と現実主義の間で揺れ動くことなく、実用性と社会的価値の両立を目指すアプローチが、単なる妥協ではなく積極的な選択であることを確認することができたのです。